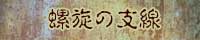螺旋の支線
来たくなかった。来たくないのだが、脳内に発生した鉄道の事は確認しておく必要がある。見ておく必要がある。
本線から分岐した単線を走ってきたチョコレート色の車両は、どこで探してきたのだろうというくらいに古い。ぼろぼろと言ってよい。
5両連なった古い電車が目の前に止まる。色も形も揃っていない寄せ集めの編成。線香臭い風が吹いている。
地上の直径が十数キロの大きなすり鉢形の深い穴。かすかに硫黄の匂いがする。線路は穴にそって螺旋状に下っていく。信号は赤である。
周囲にとまっているワゴンや乗用車から、ここから乗る乗客たちが出てくる。皆一様に白い服を着ている。老人が多い。家族に手をひかれ、ゆっくりと歩いて電車に乗っていく。
曇天である。厚い雲に覆われて時刻がわからない。艶のない車体の色が、周囲の殺伐とした風景に妙に合っている。
閣僚経験者も乗っている、というひそひそ話が聞こえてくる。窓に目をやるが、誰なのかわからない。みな一様に無表情だ。暗くも明るくもない表情が並んでいる。
地味な服装の僧侶が現れ、電車に向かって何か話をしている。家族らしい人々が遠巻きにそれを聞いている。
僧侶の話が終わり、若い駅員が笛を吹く。信号が青になっている。
ゆっくりと、重い音を残して、古い電車が螺旋の線路に入っていく。僧侶と家族が静かに見送る。
下り坂に電車が消えていく。
電車も乗客も、ここには二度と戻らない。
人々は去って行き、最後に残った駅員も軽乗用車に乗り込みながら言う。
「帰りの電車はありませんよ」
わかってる、と手をあげると、呆れたという顔で走り去る。
錆びた線路に沿って歩いてみる。下り坂の行く手はガスに覆われ風景に溶け込んでいる。
目を閉じ、レールに耳をつけてみる。遠くかすかに電車の走る音がする。ような気がする。
瞼に無表情の乗客たちが浮かんでくる。
涙があふれ、錆びたレールにしみていく。
誰かが近くにいるような気がして立ち上がる。
誰もそこにはいない。曇天の下、ただ、風が吹いている。