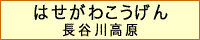長谷川高原
制服姿の初老の男性が笑顔で迎えてくれた。
東北のとある町まで取材に来たのは、「長谷川高原」駅の噂を耳にしたからであった。
「長谷川高原」はJRの線路際にある広い敷地の家である。まわりは林に囲まれ、線路に面した庭に、長さ15メートルほどの「ホーム」がある。ベンチがあり上屋があり、堂々とした白い駅名票「長谷川高原」が立っている。
初老の男性、長谷川さんは、仕事を引退してからこの土地を買い、小さな家に奥さんとふたりで住んでいる。
家自体は贅沢な作りではないが、広い土地を利用してホームを作り、個人的な「駅」にしてしまったのである。
「失礼」
腕時計を見た長谷川さんはそう言って席を立つと、ワイヤレスマイクのスイッチを入れた。
「1番線、列車が通過します。ご注意ください」
家の脇を普通列車が通過していく。
「ぜんぶ通過なんですけどね」
長谷川さんが笑う。
ホームと線路の間はそれなりに広いし、柵もあるわけで、万が一列車が停まったとしてもこの「駅」から乗ることはできない。「それでもいい」と長谷川さんは言う。
「子供の頃から鉄道が好きでね、模型だの何だのいろいろやりました。でも結局本物を見ていたいんですね」
それで個人的な架空の駅を作ってしまった。
「ホームの掃除をしたり、時刻表を確かめて、列車を見送ったりね。本物の車両を勝手に私の鉄道にしている感じですかね。もともと駅のもっている雰囲気は好きでしたから」
奥さんがコーヒーをいれてくれた。
「本当に飽きないのかしら、と思いますよ」なかば呆れ顔だが、夫婦関係は良さそうだ。
「この部屋は駅の事務室でもあり、駅前喫茶でもある。そんな空間なんです。空想は自由ですから」
壁には駅名票の横に制服姿で立つ長谷川さんの写真。背景には「通過」する特急が写っている。
「それっぽいでしょう?」
写真を見ながらおいしそうにコーヒーを飲む長谷川さんは幸せそうだ。
「嘘の駅を介して、自分の空想と本物の鉄道が結びつくというのかな、子供っぽい遊びですけどね」
帰りに、記念に持っていってくれと長谷川高原駅の「入場券」を貰った。
「ほんの遊びでね、知り合いの名刺屋に100枚くらい刷ってくれと言ったら間違えて1000枚持ってきた」
長谷川さんに「隣の駅」まで車で送ってもらった私は本物の普通列車に乗り、「長谷川高原駅」を通過した。長谷川さんの空想と私の現実がリンクする瞬間であった。
ちなみに、「高原」は奥さんの旧姓なのだそうだ。長谷川高原は、二人の名字を並べた名前の架空駅だったのだ。